これらの問題は、筆記具の先端の形状の変化に対応して書けるかどうかということであり、そのためには筆記具の回転運動が重要な意味を持ちます。
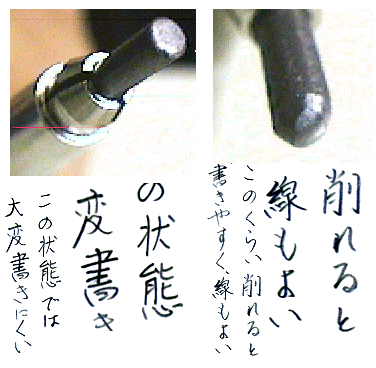 まず、鉛筆の先端を見てみましょう。芯を削っていない鉛筆の先は、右図の左のようになっています。当然、このままでは書きにくいことになります。しかし、そのまま書いていくと、線は太いものの、かなり書きやすい状態になります。図の右の状態です。先が丸くなっていることと、もう一つは多面体的に見えることに特徴があります。
まず、鉛筆の先端を見てみましょう。芯を削っていない鉛筆の先は、右図の左のようになっています。当然、このままでは書きにくいことになります。しかし、そのまま書いていくと、線は太いものの、かなり書きやすい状態になります。図の右の状態です。先が丸くなっていることと、もう一つは多面体的に見えることに特徴があります。鉛筆、シャープペンシルといった先端の形状が変化する筆記具をうまく使いこなすためには、面をどのように作り、使っていくかということが大切であり、そのために筆記具を(筆記している際の視線から見て)反時計回りに回転させる必要が生じます。
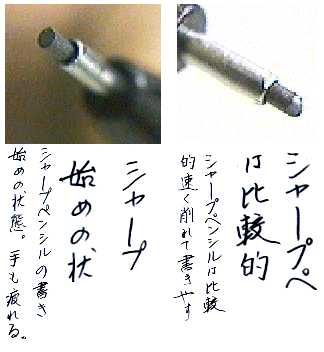 当然シャープペンシルの場合も、同様なことが言えるでしょう。右の図は、0.5mmの芯を使ったシャープペンシルです。先の鉛筆ほどではありませんが、おろし立ては書きにくく、書いているうちに先が削れてきて、書きやすくなります。この場合、多面体的な形状ははっきりしませんが、ほぼ同様に考えて良いと思います。鉛筆は芯まで削って先を細くしてから使うのが普通ですが、シャープペンシルはそのまま使います。そのかわり、もともと芯が細いために、早く書きやすくなりますね。
当然シャープペンシルの場合も、同様なことが言えるでしょう。右の図は、0.5mmの芯を使ったシャープペンシルです。先の鉛筆ほどではありませんが、おろし立ては書きにくく、書いているうちに先が削れてきて、書きやすくなります。この場合、多面体的な形状ははっきりしませんが、ほぼ同様に考えて良いと思います。鉛筆は芯まで削って先を細くしてから使うのが普通ですが、シャープペンシルはそのまま使います。そのかわり、もともと芯が細いために、早く書きやすくなりますね。シャープペンシルの場合、細い芯のおかげで、回転運動をしなくともそれほど太くなりませんが、そのかわり回転運動なしでは線がきれいに引けないという症状が起こってきます。多くの小学校では、シャープペンシルを用いないようにいう理由として、鉛筆を使った方が筆記具の使い方がうまくなるからだ、と考えているところが多いようです。その理由は、鉛筆を用いた方が、回転運動により筆記面を作るという意識ができやすいということなのです。
ちなみに、大人になって、この回転運動と面を作ることができないという方もいらっしゃるでしょう。その場合、試しに0.3mmのシャープペンシルを使ってみて下さい。0.3mmくらいになると、斜めに削れた形状・サイズが、線の太さとして適当な太さとなり、回転して面を作らなくても、そのまま書き続けられます。「0.3mmは折れやすい」って、いえいえ、芯の製法は日々進歩していてずいぶん強くなっていて、書きやすいはずです。
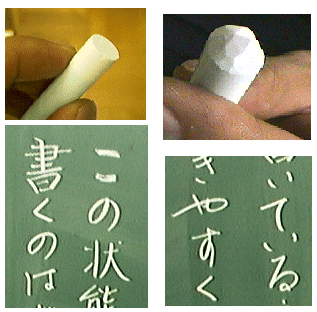 さて、鉛筆より太く、しかもシャープペンシル同様削らずに使う筆記具(?)が、チョークです。チョークの場合、右図のように多面体的形状がくっきりとあらわれます。鉛筆・シャープペンシルで回転運動を(無意識に)理解している人は、チョークを使うのにも早く慣れるようですが、そうでない人の場合、なかなかうまく書けないようです。
さて、鉛筆より太く、しかもシャープペンシル同様削らずに使う筆記具(?)が、チョークです。チョークの場合、右図のように多面体的形状がくっきりとあらわれます。鉛筆・シャープペンシルで回転運動を(無意識に)理解している人は、チョークを使うのにも早く慣れるようですが、そうでない人の場合、なかなかうまく書けないようです。
そもそも、チョークの先をほんの少し削った状態で売り出したら、便利だと思うのですが、まだ見かけたことはありません。どっかの会社が特許をとって、それを使っていないのでしょうかね? 私は特許/実用新案申請してませんよ。^^;;
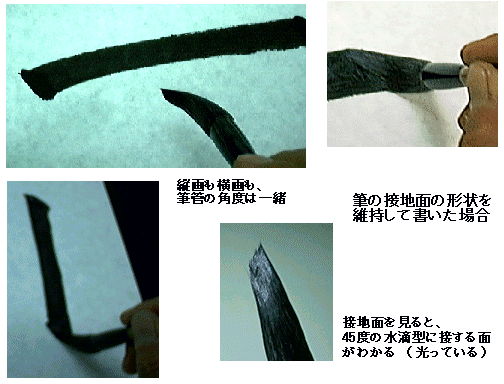 最後に、毛筆の場合を考えてみます。私の別の文章にも書いていますが、楷書の場合、左45度程度に傾いた水滴状の形状が運動することで、線が成立します。右図のように、それは横画も縦画も同様です。自然な状態で持った際の筆管の傾きのまま書けば、こうなるわけです。また、横画・縦画を書き終えた状態の筆をそのまま持ち上げた際の写真も載せておきました。光が当たっている面の形状がまさにこの形状になっています。
最後に、毛筆の場合を考えてみます。私の別の文章にも書いていますが、楷書の場合、左45度程度に傾いた水滴状の形状が運動することで、線が成立します。右図のように、それは横画も縦画も同様です。自然な状態で持った際の筆管の傾きのまま書けば、こうなるわけです。また、横画・縦画を書き終えた状態の筆をそのまま持ち上げた際の写真も載せておきました。光が当たっている面の形状がまさにこの形状になっています。要するに、この形状を維持した状態で書けない人の場合、最初の質問の
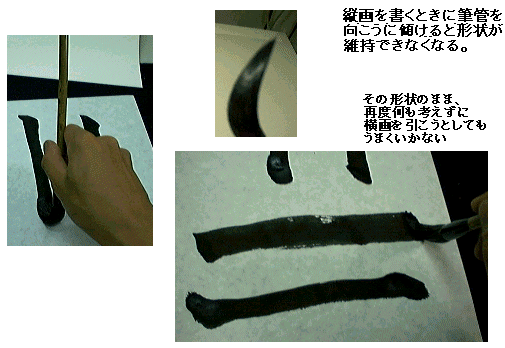 この形状が維持できない理由も様々考えられます。ここでは、もっともよく見られる例を挙げておくことにいたします。
この形状が維持できない理由も様々考えられます。ここでは、もっともよく見られる例を挙げておくことにいたします。
<---------------------
選択のページに戻る
-------------------->
<=========================
押木研究室に戻る
========================>