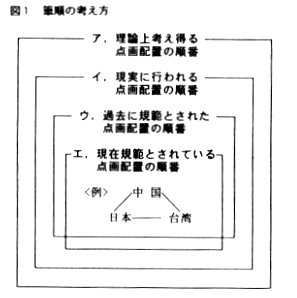 手書き文字の研究の中で、筆順研究は比較的進んでいる分野といえよう。その研究方法には、比較研究・歴史研究・実態調査などがある。またその研究対象は、筆順に関する社会的規範・指針は該当するものと日常使用の筆順とに分けられる。これらについては、押木
手書き文字の研究の中で、筆順研究は比較的進んでいる分野といえよう。その研究方法には、比較研究・歴史研究・実態調査などがある。またその研究対象は、筆順に関する社会的規範・指針は該当するものと日常使用の筆順とに分けられる。これらについては、押木『筆順指導の手びき』を対象とした筆順構造の分析
金沢大学教育学部附属中学校 礒 野 美 佳
1
.はじめに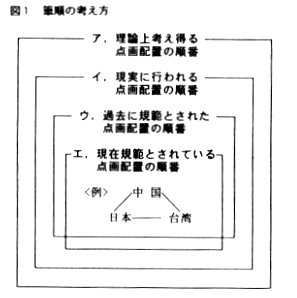 手書き文字の研究の中で、筆順研究は比較的進んでいる分野といえよう。その研究方法には、比較研究・歴史研究・実態調査などがある。またその研究対象は、筆順に関する社会的規範・指針は該当するものと日常使用の筆順とに分けられる。これらについては、押木
手書き文字の研究の中で、筆順研究は比較的進んでいる分野といえよう。その研究方法には、比較研究・歴史研究・実態調査などがある。またその研究対象は、筆順に関する社会的規範・指針は該当するものと日常使用の筆順とに分けられる。これらについては、押木
本研究は、筆順の分析方法を提案するものである。具体的には、筆順の「入れ子型表記」による分析方法を検討し、この表記方法により社会的規範・指針である『筆順指導の手びき』
2に掲載されている筆順を表記して、分析を行った。その分析結果を筆順だけでなく漢字の書字運動、漢字構造という視点から考察することで本表記法の有効性を示す。なお本論文では、磯野浩之
3の「筆順とは、文字を書く過程において点画を配置していく順番である」という定義に従って筆順を捉える。図1は、筆者の「筆順の考え型」であり、分析対象である『筆順指導の手びき』の筆順は、エに位置する。
2
.筆順の「入れ子型表記」の方法について
2
-1「入れ子型表把」のねらいと概要まず、「入れ子型表記」について説明する。筆順の「入れ子型表記」は、押木ら
4によって提案されている筆順表記法である。本表記にあたり、次の2点を満たすことに目標とした。・目的を限定しない汎用の分析が可能であること。
・コンピュータによる処理・分析が可能であること。
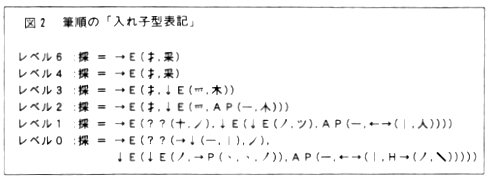 本研究における「入れ子型表記」とは、図
本研究における「入れ子型表記」とは、図
2
-2 表記のための3要素2
-2-1「基本点画」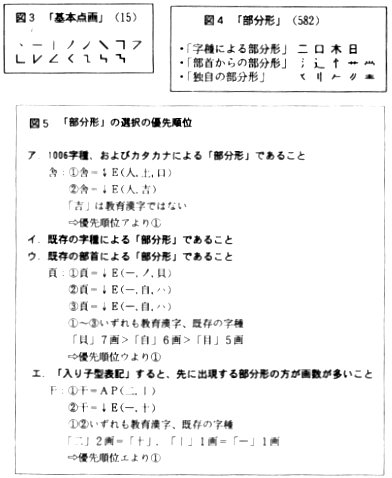 筆順表記に必要なものとして
筆順表記に必要なものとして
一基本点画の捉え方については、
1画を一基本点画の単位とする。ただし、現実には2画を1ストロークで筆記することもあるし、逆に1画を2ストロークで筆記することがある。例えば、「比」の総画数は4画であるが、左部を3ストロークで書くという現象があることは、前述の掘が述べている。一基本点画の形伏については、次の通りである。実際の書字の際に点画の方向は、様々な角度で筆写されている。まず本表記において「基本点画」の形吠を、
45度を基準に作製した。次に、学年別漢字配当表所収の教科書体(以下、
1006字種)に見られる点画をいずれかに分類した。ある点画が、いずれの「基本点画」に該当するのか決定しにくい場合は.識別要素という観点から分類した。例えば、「川」の第
1画は「ノ」「l」のいずれかと考えられるが、識別要素としては後者と考えた。また、「氏」の2画目ハネは字種の識別要素を含むものであると判断し、「レ」とした。しかし、4画目ハライは識別要素を含まないと判断し、「\」とした。
2
-2-2 「部分形」次に、
100時種の筆順を、レベル別(後述)に表記するため「部分形」を536種定義する。漢字の多くは、もともと多くの部分に分けることができる。本研究における「部分形」は、図4に示したように既存の字種(以下「字種による部分形」)・部首(以下「部首からの部分形」)・それ以外の独自の部分(以下「独自の部分形→)からなる。なお「独自の部分形」は、本表記のために作ったものである。字種によっては、幾通りもの「部分形」に分割できる。そこで、図5のように優先順位を定義し、それに従い「部分形」は、レベル1~6のいずれかに分類される。レベルとの「部分形」の数は以下の通りである。レベル
1の「部分形」:85レベル
2の「部分形」:170レベル
3の「部分形」:118レベル
4の「部分形」:126レベル
5の「部分形」:34レベル
6の「部分形」:32
-2-3「規則記号」筆順表記に必要なものとして
13の「規則記号」を定義し、図6に示す。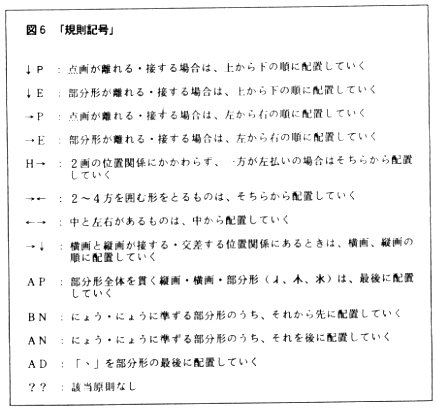 定義にあたっては、『筆順指導の手びき』の「筆順の原則」を参考にした。しかし、久米
定義にあたっては、『筆順指導の手びき』の「筆順の原則」を参考にした。しかし、久米
2
-3 レベル表記 本研究では、字種およぴ「部分形」の筆順をレベル別に表記した。図
本研究では、字種およぴ「部分形」の筆順をレベル別に表記した。図
まず、「部分形」のレベル表記について説明する。本研究では「部分形」について、レベル
6~1の段階を設定した。「深」を例に説明する。○の中に示した数字は、その「部分形」のレベルである。「*」は、レベル4の「部分形」であるが、「*」(レベル1)、「ハ」(レベル1)、「木」(レベル3)といった低レベルの「部分形」から構成されている。またさらに分割していくことで、「*」は「l」(レベル0)「*」(レベル0)といったように最終的には「基本点画」にいたる。「基本点画」はレベル0の「部分形」ともいえる。次に、
1006字種のレベル表記について説明する。1006字種は、レベル6~0の段階表記が可能となる。「深」はレベル4が最も高レベルの表記であるため、レベル4以上の表記は変わらない。レベル3の「部分形」である「木」を含む段階をレベル3表記、レベル2の「部分形」である「人」を含む段階をレベル2表記と呼ぶ。つまりレベルⅩ表記は、レベルⅩの「部分形」とそれより低レベルの「部分形」・「基本点画」によって構成される。「部分形」を用いずすべて「基本点画」で表記したパターンをレベル0表記と呼ぶ。レベル表記を行うのは、段階を追った筆順の構造を分析するためである。なお、レベル表記は次の手順によって行った。まず、すべての字種・「部分形」をできるだけ高レベル表記した。次に、コンピュータにて
sedを用い低レベルヘと展開していき、レベル0にまで展開を行った。3
.分析対象と分析項目筆順の「入れ子型表記」の有効性を検討するために、分析を行った対象と分析項目について概説する。
3
-1分析対象対象字種は、
1006字種とする。筆順を表記する前提となる筆順は、『筆順指導の手びき』にあるものとする。『筆順指導の手びき』刊行後に加えられた25字種については、「筆順の原則」によった。なお、『筆慣指導の手びき』に掲載された筆順を対象とするのには、4つの理由がある。・『筆順指導の手びき』は現代日本の書写教育のよりどころとなっている。
この筆順を対象とすることは、筆順の意味およぴ、『国語問題問答第
6集』にある「筆順指導の必要性」9の検証につながっていくであろうと考えた。3
-2 分析項目筆順の「入れ子型表記」の有効性を示すため、コンピュータにて次の項目についてカウントした。
◎「基本点画」について(対象:
1006字種)・「基本点画」の使用頻度
・「基本点画」の組み合わせの使用頻度
◎「部分形」について(対象:
1006字種)・「部分形」の使用頻度
・「部分形」のうち「字種による部分形」の使用頻度
◎「規則記号」について(対象:
1006字種、「部分形」)
4
.分析結果対象とした
1006字種を「入れ子型表記」によりレベルごとに表記し、コンピュータにて「基本点画」「部分形」「規則記号」の使用頻度をカウントした。その結果について報告し、考察を進める。
4-1
「基本点画」の使用頻度から分かること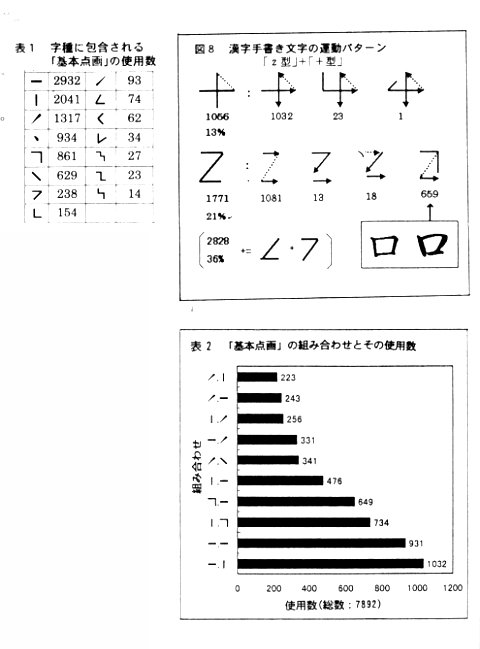 まず、
まず、
次に、
1006字種についてどのような「基本点画」の組み合わせが多いかをカウントした。「基本点画」は15あるので、2つの「基本点画」の組み合わせは、全部で225通り考えられる。表2は、そのうち使用頻度の高い10パターンの組み合わせを示したものである。この表から、「一.|」(1032)「-.-」(931)の組み合わせが多いことが分かる。「-.-」の組み合わせは、押木1が言う「Z型」運動と考えられる。また、「-.1」の組み合わせは、「+型」運動と考えられる。この「Z型」「+型」運動は、漢字手書き文字の運動パターンを示しているのではないかとの仮説を立てた。図
8は、この仮説に基づき「-.|」「-.-」の組み合わせから予想される漢字手書き文字の運動パターンを図式化したものである。「+型」「Z型」運動を含む「基本点画」の組み合わせは、「-.l」「一.一」の他にも考えられる。それらについても図中に示した。その結果「+型」運動は、使用されている全組み合わせの約1割を占めることが分かる。また、「Z型」運動については、約2割を占める。なおこの組み合わせには、楷書では「Z型」運動にならなくても、行書などの連続性のある筆記をする場合「Z型」になるであろう「¬.-」の組み合わせも含めている。さらに、「Z型」運動の一部と考えられる「∠」「*」を含めると、3割以上をも占めることが分かった。もちろん、この数値はあくまでも理論値にすぎないし、漢字の書字運動についての立証は、実際に筆記する様子を調査すべきであろう。しかし、こういった漢字の書字運動についての結果を得ることができるという点も、本表記法の特徴といえよう。
4
-2「部分形」の使用頻度から分かることまず、
1006字種の中に「部分形」の使用数、さらに「字種による部分形→の使用数を各レベルごとにカウントした。その分析結果を報告し、この2つの結果から何がいえるのか考察を進める。
4
-2-1字種に包含される「部分形」の使用頻度まず
1006字種の中に「部分形」が何回使用されているかをレベルごとにカウントした。その上位について表3に示す。左から右にレベル1~6の順で、また上から下に「部分形→の使用頻度が高い順で並べた。なお、「一」は「-」のみで表記できるため、例外として除いた。レベル
1~6の順に、各レベルにおいて使用頻度の高い「部分形」を見ていく。レベル1では、「口」「二」「人」「十」が多い。レベル2では、「*」「*」「*」が多い。レベル3では、「口」「日」「木」が多い。レベル4以上では「木」「イ」「口」「*」が多い。このうちレベル3以上に多く見られる「口」「木」については「字種による部分形」であり、次に改めて考察する。さらに、レベル4以上について細かく見ると、「口」「目」を「字種による部分形」として包含する「部分形」が多いことが分かる。次に、レベル
4以上で多い「部分形」の「木」「イ」「三」は、「部首からの部分形」であり、これらから、レベル4以上に表記すると扁旁構造が多くなるのではないかと推察できる。このことについては、「『規則記号』の使用頻度から分かること」の項目で考察を進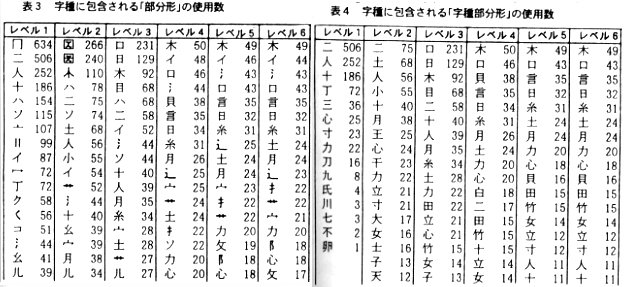 める。
める。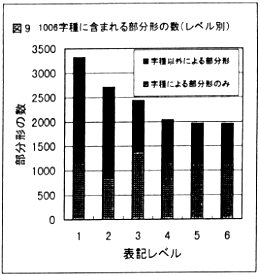
次に、「口」「木」などの「字種による部分形」が
1006字種の中に何回使用されているかをレベルごとにカウントした。その上位について表4に示す。左から右にレベル1~6の順で、また上から下に「字種による部分形」の使用頻度が高い順で並べた。そのまま、各レベルにおいて使用頻度の高い←字種による部分形」を見てい。レベル
1と2では、いずれも「二」「人」が多い。レベル3以上では、いずれも「口」「木」が多い。ここでレベル
4以上で多数使用されている「口」「目」に注目する。先の表3においてレベル1で使用頻度の最も高い「口」は、レベル2で使用頻度の高い「*」「*」の「部分形」である。またこれらは、レベル3で使用頻度の最も高い「口」「日」の「部分形」である。同様にこれらは、レベル4以上で「字種による部分形」として多く使用されている。全体にレベル3以上では、「字種による部分形」である「部分形」が多い。1006字種に包含される「部分形」に対する、「字種による部分形」の比率をレベルごとに分析した結果が、図9である。レベル1と2において、「字種による部分形」の上坪は、30%程度でしかないが、レベル3以上においてその比率は60%近くにもなる。この示す内容については、次節以降で考察を進める。
4
-2-3「部分形」検索の持つ意味
このようにレベルごとに字種に含まれる「部分形」を検索し、その使用頻度を自動計算できるのは、本表記法の特徴といえよう。この特徴は、筆順分析以外にも生かせるであろう。例えば、「部分形」の使用数をカウントすることにより、どの「部分形」を包含する字種が多いか明らかになった。この結果から、書写指導においてどの字種に指導の重点をおけばいいのかという手掛かりが得られた。筆胤謀外の書写指導の内容論・指導論に役立つであろう点も、本表記法の特徴といえよう。
4
-3「規則記号」の使用頻度から分かること1006字種中に13種の「規則記号」が何回使用されているか各レベルごとにカウントを行い、その結果から漢字の構成要素と、漢字の学習に関する仮説を立て、それらについて考察を進める。
4
-3-1字種に包含される「規則記号」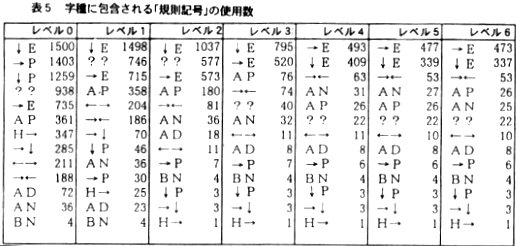
まず、全体を見る。全レベルを通じて「↓
E」「→E」が多い。次にレベル0~6の順に、各レベルにおいて使用頻度の高い「規則記号」を見ていく。レベル0では「↓E」「→P」「↓P」が多く、レベル1と2では「↓E」「??」「→E」が多い。レベル3では「↓E」「→E」が多く、レベル4以上では「→E」「↓E」が多い。「??」に注目すると、レベル3以上になると「??」は減少するが、レベル0~2では多いo「??」は、前述のように「規則記号」で説明すると矛盾を生ずるものであり、これだけは特別に学習する必要があることを示している。表5から分かったことを明確にするために、この表をもとに図10を作成した。横軸は左から右にレベル0~6の順を、縦軸は各レベルごとの「規則記号」の使用頻度を示している。まず、全体を見る。「→E」が各レベルを通じて使用頻度が高いことが分かる。次にレベル0~6の順に目を移しながら各レベルにおいて「規則記号」の使用頻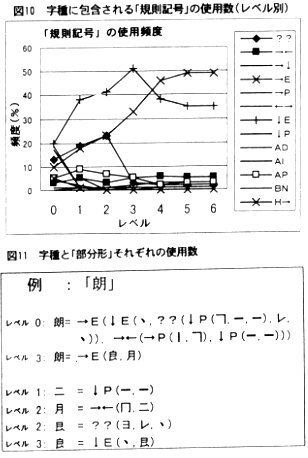 度を見ていく。レベル0と1では、数多くの「規則記号」が用いられている。レベル3以上では、「→E」「↓E」を合わせると、その使用頻度は80%以上になり、その他の「規則記号」は減少する。さらに細かくみると、次のことにも気づく。レベル3~4では「→E」の使用頻度は増加し、「↓E」のそれは減少して、逆転が見られる。レベル2~3では、「↓E」の使用頻度は急増しているが、「↓P」のそれは急減している。ここで、レベル3~4における「→E」「↓E」の逆転現象について注目し、レベル4以上では扁旁構造が多いのではないかという仮説を立てた。この仮説については、前の項目においても触れた。これについて考察を進める。
度を見ていく。レベル0と1では、数多くの「規則記号」が用いられている。レベル3以上では、「→E」「↓E」を合わせると、その使用頻度は80%以上になり、その他の「規則記号」は減少する。さらに細かくみると、次のことにも気づく。レベル3~4では「→E」の使用頻度は増加し、「↓E」のそれは減少して、逆転が見られる。レベル2~3では、「↓E」の使用頻度は急増しているが、「↓P」のそれは急減している。ここで、レベル3~4における「→E」「↓E」の逆転現象について注目し、レベル4以上では扁旁構造が多いのではないかという仮説を立てた。この仮説については、前の項目においても触れた。これについて考察を進める。
4
-3-2 漢字の偏芳構造について字種に包含される「部分形」の使用頻度の分析から、レベル
4以上では「木」「イ」「*」という偏になりうる「部分形」が多く使用されているという結果を得た。さらに字種に包含される「規則記号」の分析からレベル3~4では「→E」の使用頻度は増加し、「↓E」のそれは減少して、逆転が見られるということが分かった。これらから、レベル0~3では「字種による部分形・部首からの部分形」を構成するために様々な順番で点画を書字するが、レベル4以上ではレベル3までに使用されている「字種による部分形・部首からの部分形→によって構成される扁旁構造の字種が多くなると考えられる。このことから、レベル4以上で使用されている「字種による部分形」の「部分形」であると考えらわるレベル3までの「部分形」を学習し、あとは主要な規則性を示す「一E」「↓E」を応用して学習すればよいという、仮説が立てられた。この仮説について考察を進める。4
-3-3 学習負担の軽減化今までの分析結果からレベル
3が、鍵になっていると考える。仮説を確かめるために「朗」を例にとって考察を進める。図11を見てほしい。レベル0表記とレベル3表記を比較する。レベル0では多様な「規則記号」が用いられているのに対し、レベル3では1つの「規則記号」と2つの「部分形」のみで表記されている。レベル3の「部分形」である「良」レベル2の「部分形」である「月」をまず学習し、それを左から右に配置していけば「朗」を書くことができる。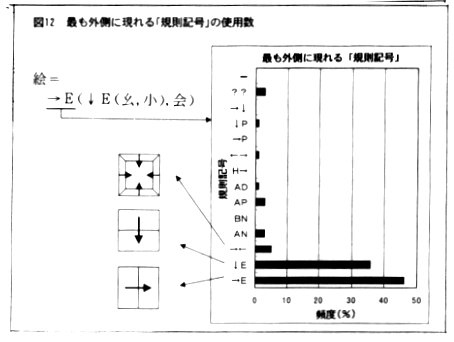 そこで、
そこで、
5
.おわりに本研究は、筆順の分析方法を提案したいという所から出発している。具体的には、「入れ子型表記」を行い、
1006字種を対象として「基本点画」「部分形」「規則記号」についてコンピュータにてその使用頻度をカウントすることで、筆順だけでなく漢字の書字運動という視点から分析を試みた。その結果次の事が得られた。◆「基本点画」について
・
2つの「基本点画」の組み合わせは、「-,l」「-,-」が非常に多い。◆「部分形」について
・レベル
4以上では、「部首からの部分形」「字種による部分形」が多い◆「規則記号」について
・低レベルでは多様の「規則記号」があるが、高レベルでは「↓
E」「→E」が多い。
この研究過程におけるレベル
6~0の表記展開、およびこれら漢字の書字運動・漢字の扁旁構造などの分析では、Sedやgrepなどの汎用の分析ツールを用いている。この結果により、本表記法は当初の目標に達していると考えられる。本表記法は、今後他の目的のための分析にも利用できる可賠性を秘めていると考えられるが、まだ完全なものとはいえない。次の点が課題として残されている。
今後、本表記法について主観的に決定せざるを得なかった部分を検討したいと考えている。中でも、字種の識別要素などについて検討を進めたい。
1
押木秀樹「手書き文字研究の基礎に関する諸考察(2)」『書写書道教育研究』第11号,1997.32
文部省『筆順指導の手びき』,1958.33
藤原宏他『書写・書道用語辞典』の磯野浩之「筆順」の項(P.276-277),1978.94
押木秀樹・礫野美住"Systematization of the Stroke order of Chinese Characters for Foreign Students",IGS975
堀千鈴・押木秀樹「手書き漢字字形の多様性に関する基礎研究『書写書道教育研究』第11号,1997.36
久米公「筆順の研究」広島大学付属高等学校『国語研究紀要』第2集,1969.97
倉内秀文「筆跡鑑定と筆順筆圧について」『文字の科学』法政大学出版局,1985.38
江守賢治『漢字筆順ハンドブック』三省堂,1982.29
文部省『国語問題問答』第6集,「国語シリーズ37」,1958.7