-
筆跡の偽造についてはその歴史も古く、紀元前1世紀のローマ帝国の時代までさかのぼるとされている。当時のローマ帝国は、共和制の崩壊とともに、野心的な武将が輩出し、公文書の偽造や権利書さらには遺言書などの偽造により、多くの富を手にいれたものが多かったと伝えられる。当然のことながら、そこでは筆跡の識別を試みたものもあるだろう。
-
筆跡に関する専門的な研究は、筆跡学または書相学(Graphology,Graphogie)と呼ばれる。この筆跡学がめざす課題には大きく分けて二つある。その一つは筆跡とそれを書いた人の性格を知ろうとするもので、性格学的筆跡学とよぶことができる。他の課題は筆跡を比べて書者の同一性または相違を鑑定することである。
情報工学における手書き文字の取扱いは近年のことであるが、文字認識研究を中心として、各種分野におよんでいる。文字認識とは、手書きもしくは印刷されている文字を打ち込みなおすことなくコンピューターに入力できたら、というものである。広く知られているところでは、郵便番号の自動読みとりシステムがその例である。コンピューターと漢字との関係については、海保や山田が分かりやすい。この文字認識の研究成果を踏まえ、筆者識別の研究が吉村他によって行われている。また、手塚らによる、毛筆体の手書き文字風の文字の生成研究も紹介しておかなくてはならない。さらに教育工学と情報工学の接点において、山崎らの書写CAIシステムの研究が進められている。以上より情報工学の分野では、機械による文字認識・毛筆風文字の生成・筆者識別・書写教育の4点からのアプローチがなされていることがわかる。
書学・書写書道教育については、省略する。他分野の研究者においても、さかのぼって各種書論や古筆見などについての論述もある。筆者は、芸術的な側面からの見方と、(文字の)歴史研究素材としての見方と、教育的な研究とは、内容的な関連は大切にしながらも、三者の区別をはっきりさせておく必要があると考える。
目的の異同
前節において述べた各分野の最終目的は、法科学であれば犯罪捜査、筆跡心理学であればカウンセリングなどということになる。ただし、大きな視点から捉えると、それらの目的は次のように整理できる。 これら目的によって、その方法は、下の図のように考えられる。ここの書かれる文字は、毎回異なった字形としてあらわれる。その字形が、図中の実現形である。そこから、字種を認識するための特徴を取り除いていくと、下方の字体素が抽出できる。この方向性が、情報工学における文字認識である。一方、個人間の差異をを抽出する方向性が、鑑定と性格理解ということになる。
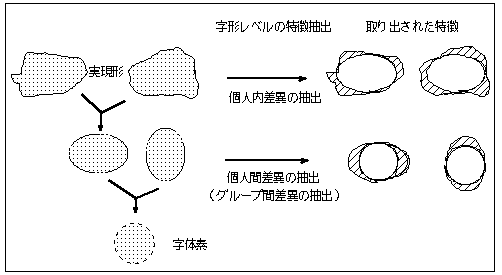
手書き文字理解は、前節において述べた各分野において、基礎として必ず必要になる部分である。また、それぞれの研究成果を互いに生かせる部分が多いと言えるかも知れない。たとえば、認識を目的とした場合にも、字形の設計理論の研究、手書き文字が個々によりどの程度違って書かれるかといった研究、筆順とそれを書く際のエネルギーに関する研究などがなされている。鑑定・識別の中心である法科学の筆跡鑑定を目的とした場合にも、筆順の手引の実行率についての報告や筆記具による違いの研究、運筆方向とその出現率の調査、漢字の分割に関する考察などがなされていて興味深い。書写教育研究は、手書き文字を生み出す最初の段階に関わる分野として、これを目的とした研究がさらに必要なのではないか。文字認識の研究者である森のつぎの文章は、手書き文字を伝統的に扱ってきた分野に身をおく筆者としては、気になるものである。
- 文字認識は、音声学といった後ろ楯をもち、その知識を十分活用している音声認識にくらべ、その基礎とも云うべき”文字学”(伝統的な、形音義を扱う意味ではない−押木注)をもたないという致命的なハンディキャップを負っている。文字認識の本質的問題を解決するために、”文字学”の基礎的研究の充実が望まれる。
<-------------------- 目次に戻る ------------------------>
<========================= 押木研究室に戻る ========================>